こんにちは!Bloomのブログへようこそ!
私は23年間教育公務員として働き、2025年3月に退職しました。
このシリーズでは、私が公務員を退職した経験をもとに、「退職後に支払うお金」についてまとめています。
第2回目の今回は、「健康保険」に焦点を当てていきます。
はじめに |「任意継続可能」と言われたら?
退職直前の2月、私は公立学校共済組合から1枚のチラシを受け取りました。そこには次のような内容が書かれていました。
「共済組合の任意継続組合員の手続きについて」
退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。
注記:任意継続組合員となるためには、退職した日から20日以内に申し出て、掛金を納入することが必要です。
「在職中とほぼ同様の・・・」と言われると、なんとなくこのまま継続するのがよさそうと感じませんか。その上、「退職した日から20日以内」と言われると、何となく焦ってしまい、そのまま手続きしてしまいそうです。
確かに、「任意継続」は優れた制度であり、大きなメリットがある人が多いです。しかし、本当にこのまま「任意継続」を選んで良いのでしょうか。
実は、健康保険には、次の3つの選択肢があり、どの選択肢が最も負担が少なく、安心して選べるかは、人によって異なります。そのため、「共済組合なら安心」、「〇〇さんもそうしているから。」ではなく、自分で調べ、自分にはどれが一番合っているのかを判断する必要があるのです。
退職前後のバタバタとした毎日の中で、「なんとなく」で選んでしまうと、大きく損をしてしまう可能性もあるため、事前に知っておくことはとても大切。
では、どのように選べばよいのでしょうか。
3つの健康保険とおすすめの選び方
始めに結論!
健康保険とは、病気やケガ、高齢化、障害、要介護といった誰もが抱えるリスクに対して、社会全体で備える仕組みのことです。例えば、皆さんが病院にかかるときに「健康保険証」を提示するのは、健康保険に加入していることを証明し、医療費の一部負担で診療を受けるためです。
公務員や会社員は、共済組合や健保組合等の健康保険を利用していますが、退職後に無職や個人事業主となる場合には、自分で健康保険を選ぶことになります。
退職後に選べる健康保険は次の3つです。
- 任意継続
- 国民健康保険
- 配偶者等の扶養
それぞれの特徴については後述しますが、まずは結論から。
私がおすすめする選び方は次の通りです。
① 公務員・会社員の配偶者等がいて、かつ退職後の年収が扶養の範囲内であれば、「配偶者等の扶養」をまずは検討する。退職直後の高額な健康保険料をさける唯一の方法。
② 自分を扶養する配偶者等がいない場合には、保険の内容が優れている「任意継続」が圧倒的に有利な場合が多い。ただし、保険料や保険内容は組合によって異なることに注意。
③ 退職後直後に「国民健康保険」を選ぶメリットは薄い。ただし、退職後2年目以降には検討の対象となる場合があるため、知識は必要。
次の項からはそれぞれの内容を詳しくまとめていきます。
「配偶者等の扶養」を選ぶ場合
まずは、健康保険料がどのくらいの金額か想像がつきますか?
私は全く想像できず、退職後に「自分の場合」を試算してみました。その結果はこちら。
| 「任意継続」を選ぶなら | 年間 約49万円 |
| 「国民健康保険」を選ぶなら | 年間 約70万円 |
健康保険料、なかなか高額です!これは任意継続や国民健康保険の保険料が、退職前の所得を基に算出されるからです。もちろん、退職時の給与が高いほど高額になります。
さらに、この保険料、現職時代の2倍になっています。なぜなら、公務員・会社員の健康保険料は、「労使折半」といって、会社(公務員なら自治体等)が半分支払う仕組みになっているから。退職したら、その分も合わせて自分で支払わなければなりません。
他にも「住民税」や「年金保険料」の支払いもあるのに…。退職後所得が大きく減る場合、これはかなりの痛手です。
そこで、公務員や会社員の配偶者等の家族がいる場合には、その扶養に入れないかをまずは検討することをおすすめします。
私の場合、夫の扶養に入ることができれば、先ほど試算した「任意継続の掛金49万円」を「ゼロ」にすることができるのです。この差は大きい!
実は、退職前「今まで一度も夫の扶養に入らず自分でやってきたんだ!退職後も扶養に入らずばりばり働くぞ!」という気概をもっていた私ですが、試算結果を見て、「こんなに高額な保険料を払うくらいなら、扶養に入れていただいてしばらくゆっくりしよう。」とあっさり心変わりしました。
もちろん、配偶者等の扶養に入るには、「年間収入が130万円未満(給与見込み)」等の条件があります。ですから、「退職後はすぐに個人事業を立ち上げて、バリバリ稼ぐぞ!」という方には向きません。あくまでも、退職後しばらくは無職、または、ゆっくり扶養範囲内で働ければよい、という場合の選択肢です。
なお、扶養の条件や補償内容は、配偶者等の加入している共済組合や健保組合によって異なります。検討される場合には、必ず確認してくださいね。
ちなみに、私の夫は教育公務員なので、公立学校共済組合の扶養条件をホームページで調べました。1月~3月は公務員としての収入が100万円以上ありましたが、「今後の収入が月額108,334円未満」との記述があり、夫の職場を通じて無事扶養認定を受けることができました。

私は、夫が公務員であり、退職後はゆっくり個人事業をスタートすればよいと考え、夫の扶養に入ることにしたよ!もし、「任意継続」の案内をもらって、そのまま手続きしていたら、50万円近く損していたかも💦
「任意継続」と「国民健康保険」の比較
扶養に入らない場合には、任意継続と国民健康保険(以後「国保」)の比較になりますが、この場合、任意継続の方が有利になるケースが多いのではないでしょうか。理由は「保険料」と「保険の内容」です。それぞれ順にみていきましょう。
まずは、保険料です。下の表を見てください。
公立学校共済組合の任意継続、国保の保険料を比較したものです。
| 標準報酬月額 | 任意継続 (扶養家族も含む) | 国保 (本人のみ) | 国保 (本人+家族3名) |
| ア 200,000円 | およそ220,000円/年 | およそ270000円/年 | およそ490,000円/年 |
| イ 300,000円 | およそ330,000円/年 | およそ410,000円/年 | およそ630,000円/年 |
| ウ 400,000円 | およそ490,000円/年 | およそ670,000円/年 | およそ900,000円/年 |
※任意継続掛金は令和7年度の例 ※国保は、筆者の居住自治体の例。実際には自治体により保険料が異なることに注意。 ※国保の家族3名は無職として試算。 ※国保試算時の年収は「標準報酬月額」に16.4を乗じて計算。 ※ウには、介護掛金を含む。
この比較表によると、公立学校共済組合の任意継続と国保では、3つのパターンともに、「任意継続」の方が保険料を抑えられます。
さらに、「任意継続」には扶養の概念があるため、同じ掛金で家族を扶養することができます。
一方、「国保」には扶養の概念がなく、健康保険に加入する家族の数に応じて保険料が高額になります。
つまり、扶養家族が多ければ多いほど、「任意継続」の優位性が高まるということです。
次に、保険の内容です。下の表は公立学校共済組合と国保の比較です。

この表から分かる通り、公立学校共済組合の任意継続は国保と比べてかなり内容が充実しています。
国保のシンプルな保険給付に比べ、災害給付や付加給付なども充実していますし、もちろん扶養されている家族への給付も充実しています。
そういえば、私が出産した際には、「出産費」の他に「出産費附加金」が給付されましたが、あれは共済組合独自の給付だったのですね。退職後であっても、2年間これらを含む手厚い給付を受けられるのは大きいですし、退職後にも「公務員として働いた恩恵」を感じられるかもしれません。
このように、公立学校共済組合の場合、保険料、保険の内容のどちらをみても、「国保より任意継続」にメリットがありますね。ちなみに、このような「短期給付」に加え、「一部の福祉事業(特定健康診断、特定保健指導、山の家・海の家利用補助等)」の利用も可能です。

公立学校共済組合の任意継続と国保を比べると、掛け金、保険の内容ともに「任意継続」の圧勝だね!
ただし、いくつか注意点もあります。
まず、比較対象となる国民健康保険料は、自治体によって金額が大きく異なるという点。今回は、私の住む市区町村で試算しましたが、実際にはこの後に紹介する方法などを使い、ご自分が退職後に住む市区町村で試算し、保険内容とともに比較してください。なお、離職理由や所得状況によっては国保料が軽減される場合もあるため、自己のケースが該当するか迷う場合には、お住まいの自治体(国保担当)にご相談ください。
また、ここでは公立学校共済組合の任意継続の例をあげましたが、共済組合や健保組合によって、掛け金や保険の内容が異なります。また、同じ公立学校共済組合であっても、年度によって内容が変更になる場合があります。手続きをする前に、それぞれの共済組合や健保組合等で「自分の場合」を確認してください。
次に、任意継続の掛金は「退職時の標準報酬月額」を基にして計算されるため、1年目と2年目がほぼ同じ掛金になります。しかし、国保の保険料は「前年の収入」を基にして計算するため、退職後1年目に収入が大きく減った場合、2年目の保険料が大幅に安くなる可能性があります。そのため、2年目以降には、必ずしも「任意継続」が有利とはいえません。
最後に、「任意継続」は、退職後2年間のみ利用できる制度です。3年目以降は、再び「配偶者等の扶養」か「国保」を選択しなければなりません。
自分の任意継続掛金を試算してみよう!
実際に、任意継続の掛金を試算してみましょう。試算には次の式を使用します。
「標準報酬月額」は給与明細に記載されており、任意継続の「掛金率」については、公立学校共済組合のホームページで確認することができます。
ただし、算定に使用する標準報酬月額には上限があること、年齢によって介護掛金の扱いが異なることから、下の「任意継続掛金早見表」を使うのが分かりやすいです。

まずは、ご自身の「標準報酬月額」を給与明細で確認し、該当する等級を探しましょう。後は、表を横に見ていくだけで、掛金を確認することができます。
表の脚注にある通り、40歳~65歳の場合には介護掛金を納付するため「合計」のらん、それ以外の年齢では「任継掛金」のらんが実際の掛金となります。
ここで特筆すべきは、「標準報酬月額」が380,000円を超えると、任意継続掛金はそれ以上上がらないということです。標準報酬月額が高くなりがちな40代以降には、任意継続がさらに有利になることが分かりますね!
自分の国民健康保険を試算してみよう!
次に、「国民健康保険」の保険料を試算してみましょう。
国保は市区町村等が運営しており、自治体によって保険料が異なります。
おすすめは、このサイト。使い方は簡単です。
まず、シミュレーションを希望する自治体(退職後の居住地)を選択します。
次に、加入者の人数を選択します。自分だけの場合は「1人」を、自分の他にこれまで扶養していた配偶者や子供がいる場合は、その人数を加えて選択します。
最後に年収を入力します。公務員としての収入は、「給与収入」のらんに入力します。直近の源泉徴収票の「支払金額」を入力しましょう。給与収入以外の収入がある場合や、扶養する家族に収入がある場合には、それらも入力してください。また、自分と家族の年齢区分も正しく選択しましょう。
以上で、国民健康保険料の年額が算出されます。
サクッと試算できますよ!
おわりに | 健康保険 私の選択
最後に、私の選択をご紹介して、まとめにかえます。
「任意継続」の謎の安心感?に思わず手続きしそうになった私ですが、退職してすぐに一度落ち着いてそれぞれのメリット・デメリットを調べ、保険料も試算してみました。
| 保険料 | メリット・デメリット | |
| 任意継続 | 約490,000円 | ◎ 扶養家族がいても同じ保険料。 ◎ 保障が手厚い。 △ 1年目に所得が減っても掛金が下がらない。 |
| 国民健康保険 | 約700,000円 | ◎ 退職後に所得が減るなら2年目は安くなる △ 退職直後は保険料が高くなりがち。 △ 扶養家族がいる場合は、さらに保険料UP |
| 配偶者等の扶養 | 0円 | ◎ 保険料は不要 △ 退職後の収入を扶養範囲に納める必要あり △ 夫の勤め先に収入等に関する書類提出あり |
私の場合、①扶養家族がいない(子供は夫の扶養) ②退職後の個人事業はゆっくりスタートでOK という二つの理由から、「夫の扶養に入る」ことを選択しました。ただし、退職後2年目以降は、働き方に応じて国保への切り替えも検討する予定です。
なお、配偶者等の扶養に入る場合には、その勤め先に自分の収入等に関する書類を提出しなければなりません。これは、扶養認定を受ける以上当然のことですが、人によっては抵抗がある場合もあるかと思い、「デメリット」として加えました。

「任意継続」の案内をもらったときには、よくわからないまま手続きしそうになりましたが、色々と調べたことで、私にとっては最適解ではないと判断しました。納得できる選択をするためには「試算」が欠かせませんね!
「退職後に支払う3つのお金」の中で最も難しいと感じたのが、この「健康保険料」でした。「人による」「自治体による」「健保組合による」とひとくくりにできない要素が多いからです。
この記事を書くのにも、思いのほか時間がかかってしまいましたが、読んでくださった皆さんの選択を少しでもお手伝いできたらうれしいです。
3回目となる次回は、「年金保険料」についてまとめる予定です。第1回の「住民税」とともに、シリーズで読んでいただくと、さらに理解が深まります。ぜひ読んでみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
ブログ更新のお知らせは、X(旧Twitter)で行っていますので、興味を持っていただいた方はぜひフォローをお願いします。
「この記事が役に立ったよ!」と言う方は、上のバナーや下のグッドマークをクリックして応援していただけるとうれしいです♪
Bloomのブログにお越しいただき、ありがとうございました!
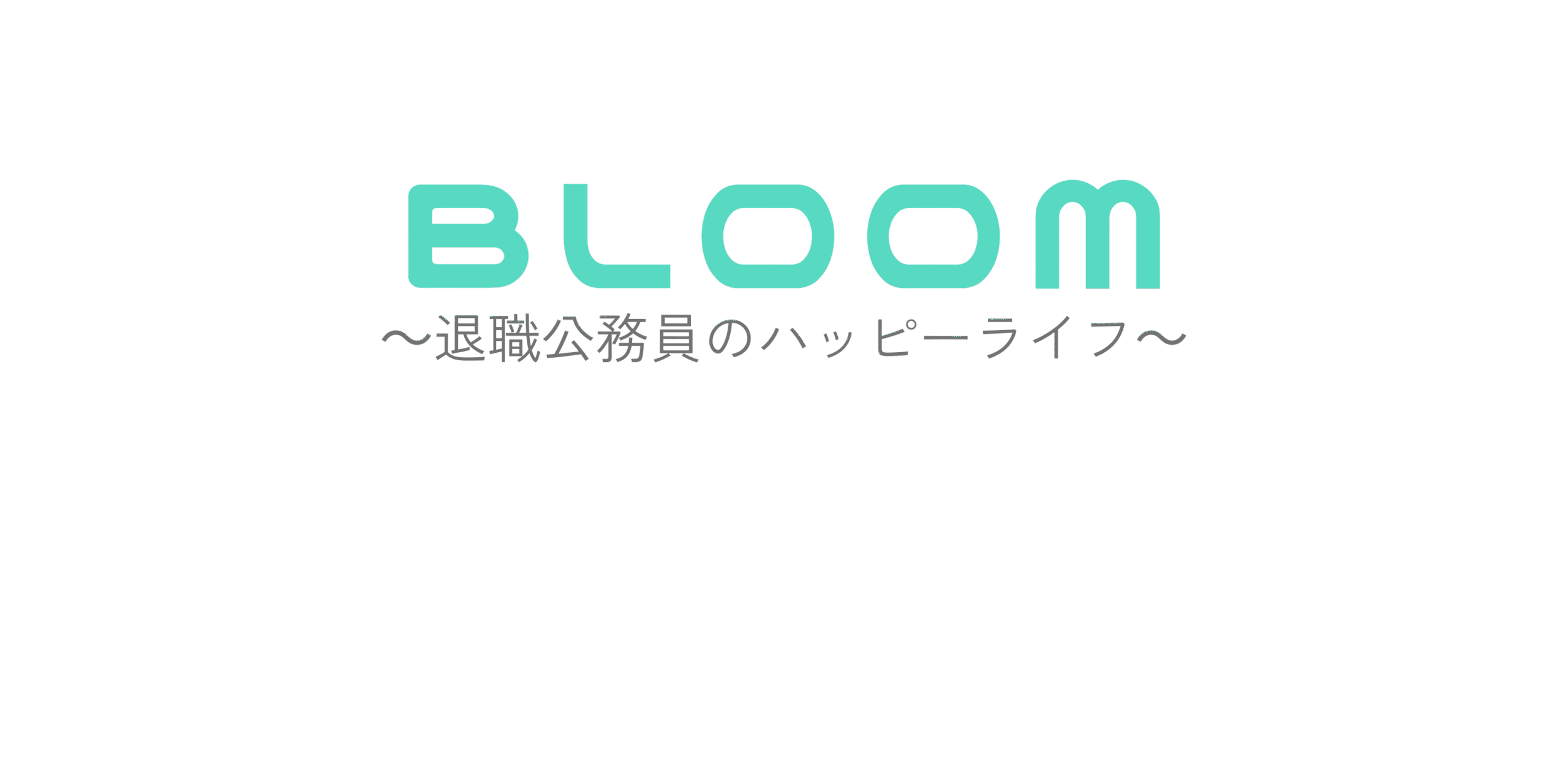

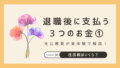
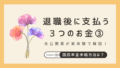
コメント